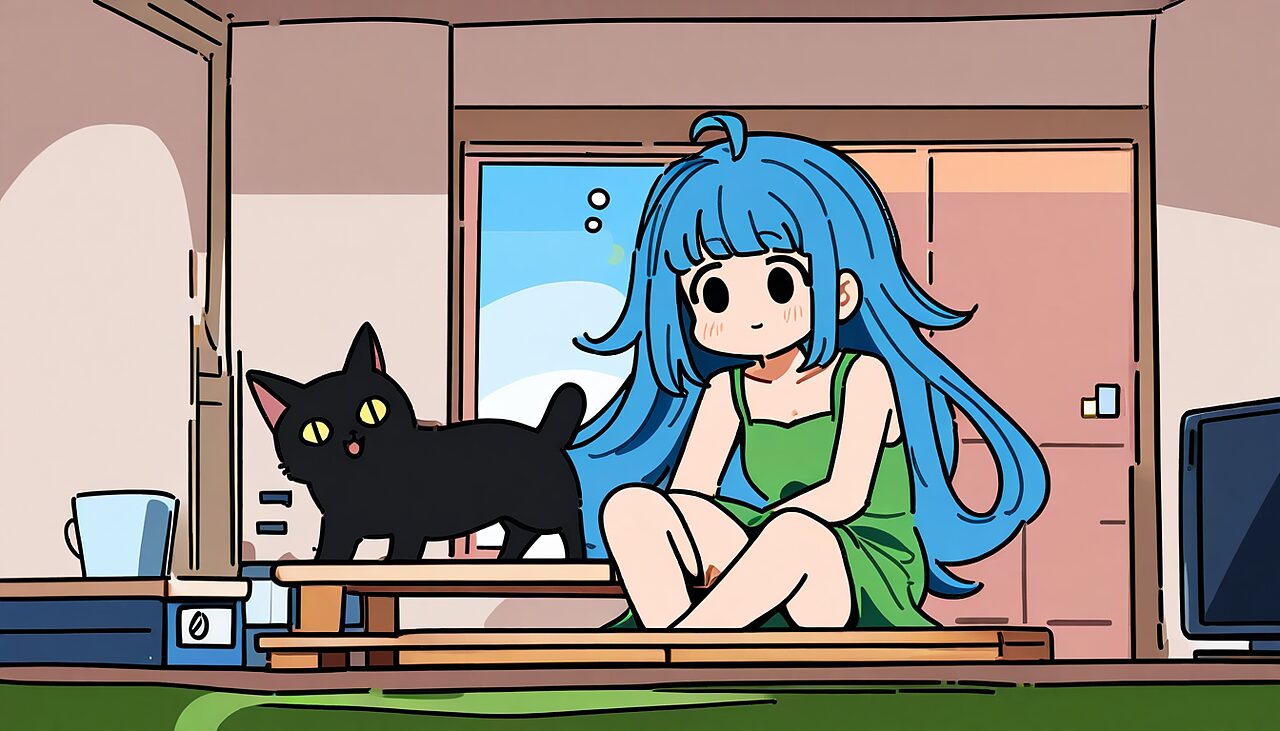かつて絵を描くという行為には時間がかかった。感情が乗り魂が宿った。誰かに「すごい」と言われるまでに幾晩も描き直し何枚も破り捨てるような過程があった。
しかし今、画像生成AIの登場によってその世界は静かに終わりを迎えつつある。
スポンサーリンク
画像生成AIがもたらしたもの
画像生成AIは確かに便利だ。数秒で完成するイラストは圧倒的なスピードとクオリティを誇る。アイディアをすぐに形にできることで制作の効率は飛躍的に高まった。
誰かが何十時間もかけて描いた構図や色使い独特の線の癖をAIは無断で学習している。本人が知らぬうちに自分のスタイルが模倣される。盗まれたような感覚を覚えるのも無理はない。
分断される創作の現場
この状況に絵描きたちは強い拒否感を抱いている。AIを使っただけで攻撃されるいわば魔女狩りのような空気が生まれているのも事実だ。一方でAIを使う者たちは「技術革新だ」「これも表現の一つだ」と言う。
その議論はどこまでも平行線をたどり分断だけが深まっていく。
スポンサーリンク
世界はAIを受け入れつつある
一度生まれてしまった技術はもう「なかったこと」にはできない。どれだけ否定されてもどれだけ反発があっても、それが便利で強力であればあるほど社会の中に静かに確実に浸透していく。ゲーム業界・広告業界・映像制作……どの分野でも画像生成AIの導入は進み生産性は大きく向上している。
欧米や中国ではAIを「当たり前の道具」として使いこなす社会が形成されてきている。コストの削減、スピードの加速、デザインの多様性、どれを取ってもAIを使う方が効率的だ。
AIを受け入れることだけが正しいとは限らない
だからと言ってAIを受け入れることだけが正しいとは限らない。人間の手で描くという事、そこに時間と感情を込めるということ。
効率よりも魂を選ぶ。便利さよりも矜持を選ぶ。
「自分で描く」という営みがたとえ時代遅れと呼ばれようともそこには確かに「魂」が宿る。
上手いか下手かではない。速いか遅いかでもない。
手を動かし、悩み、描き続けるということがAI時代の日本の矜持なのかもしれない。